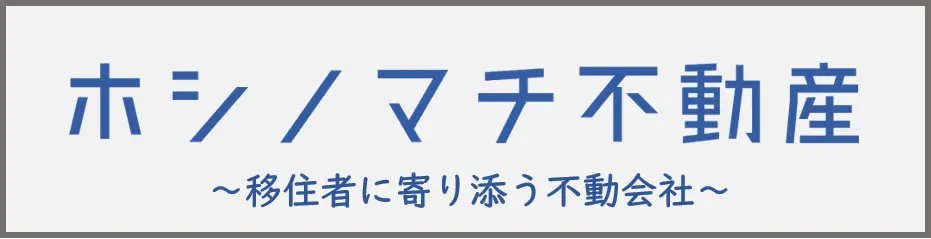先日訪ねたプルーン農家の佐々木さんから伺ったお話です。
「跡継ぎがいない。あと2年と考えているが、教えるから誰か継いでもらえないか。」
佐久市では今、農家の跡継ぎ問題が深刻化しています。
なぜ、農家を継ぐ人が少ないのか。
主な理由としては、高齢化、長時間労働、収益性の難しさなどが挙げられます。
昔の農業は、大家族や親戚、近所の人々が協力し合い、即戦力となる人手も多く、地域全体で支え合う「家業」でした。
しかし現代では、ご夫婦やご兄弟だけで営むケースが多く、人手不足は深刻です。
その結果、作業できる人手が足りず、外部の力に頼らざるを得ない農家が増えています。
「田んぼはあるけれど、人に任せて自分の食べる分だけもらっているんだよ」と高齢の農家の方のお話を聞いたことがあります。
もくじ
家庭菜園に関心を持つ人が増加中!その理由とは?
深刻な後継ぎ問題の一方で、農業への関心が高まっている兆候も見られます。
実はホームセンターでじゃがいもの種芋が売り切れたり、農業イベントに多くの方が参加したりと、「作物を育てること」に関わる人は増えているようなのです。
これは、農業が持つ心と体へのポジティブな効果にも関係しているのではないかと考えています。
土いじりには、ストレス軽減や免疫力向上、運動効果、精神安定作用など多様なメリットがあります。
また、午前中に太陽の光を浴びることで、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンを増やす効果も期待できます。
こうしたことから、家庭菜園を始めるご家庭も多く、「食べるものに関わりたい」という潜在的なニーズは高まっていると言えます。
この個人の関心の高まりというのは、地域にとって追い風となるのではないかと考えています。
「一人で背負わない」新しい農業のカタチ
労働人口が減っていく現代において、一人がすべての責任を負い、生活を維持していくのは難しい時代です。
一方で、
- 耕せる土地がある
- 技術を持った先人がいる
- 作物を育てることに関わりたい人がいる
という状況を考えると、継続できる可能性はあるのではないでしょうか。
むしろ、先人の知恵や知識に新しい形を加え、実行し、共に成長していく伸び代のある新しい職業だと捉えることもできます。
重要なのは「必要なときに集められる助っ人」を作ることではないかと考えています。
たとえば
・耕運機の操作ができる人
・収穫を手伝える人
・種を植える小さな手
・重いカゴを運べる人
・春や秋など特定時期だけ手伝える人など、
実は、そんな役割分担が地域では起きていたりします。
一人で背負うのではなく、それぞれができる分野での協力をしながら進める。
そんな新しいカタチで始まる農業が増えているような気がします。
実際、手伝ってくれる人の都合で、農作業が遅れるといったこともあるようです。
それが生活のために必要なものであれば、大変ですが、地域の人たちに喜んでもらいたいからといった想いでのものなので、問題ありません。
自分たちのペースでできる範囲内で取り組む。
それこそが、地域で農業を続けていく秘訣なのかもしれません。
佐久市への移住が拓く「農」の未来
農業と一口に言っても、花、果樹、野菜、米など様々な作物があります。
「就農移住」も農家の後継ぎだけでなく、農家の支援、地域協力隊、作物のブランディングなど、関わり方は多岐にわたります。
「経験がないから無理」と諦める必要はありません。
まずは農家の方の生の声を聞いたり、忙しい時期のお手伝いを体験したりして、ご自身と農業との関わり方を一緒に考えていきましょう。
佐々木さんの畑では、樹齢30年の木の隣に5年の若い苗木が植えられ、プルーンも世代交代を迎えています。

佐久市は、豊かな自然の中での生活だけでなく、農業での活躍の場は大いにあると思います。
特にプルーンは非常においしいのでおすすめです!
佐久市への移住で農業の未来を「共」に創る:新しい担い手としての可能性
佐久市では、老舗農家からの切実な声にもあるように、後継ぎ問題が深刻化しています。
しかし一方で、農作業の魅力が見直され、農業に関心を持つ人々は増加傾向にあります。
この状況を打破する鍵は、「一人で背負う」のではなく、多様なスキルを持つ「助っ人」が支える新しい農業のカタチかと思います。
耕せる土地、先人の技術、そして関わりたい人たちの力が結集すれば、継続していくのではないでしょうか。
農業への関わり方は、後継者として、地域おこし協力隊やボランティアとして、と様々です。

地域の課題の一つである農業。
そこに関わってみたいという方はぜひ一度佐久市に見に来てみてください。